海外生活から日本の学校に戻ったとき、「うちの子、漢字はもちろん、作文も全然書けない…」と悩む保護者の方はとても多いです。

作文や小論文を書くことは、帰国受験の時はもちろんですが、その後の学校生活や社会生活でも避けては通れない道です。
我が家の子どもたちは、国語は何とかなったけど、数学の文章題が大の苦手でした。



このように、国語力といっても国語だけではなく、実は全部の教科に影響が出たりするんです。
「書くのが遅い」「話せるけど文章が変」——その原因は、単なる語彙力や読解力不足だけではありません。
この記事では、海外生活で国語にブランクができてしまった小学生が、“作文力”を楽しく・自然に伸ばしていける5つの方法を、実体験ベースでご紹介します。
帰国子女が国語を苦手とする3つの理由
日本語を話せる=国語が得意、ではありません。
日本語にはひらがな、カタカナ、漢字、といった文字の種類の多さに加えて、文法もかなり複雑です。
なので、海外で英語中心の生活を送ってきた子どもたちは、国語(特に読み書き)に苦手意識を持つことがよくあります。



この章では、帰国子女がどうして国語につまづいてしまうのか、3つの理由を解説します。
会話は得意でも「日本語で文章を書く」機会が少ない
海外では日常生活や学校での会話は英語中心。
家庭で日本語を話していても、「日本語で文章を書く」経験はほとんどありません。
文章の構造や接続語の使い方を学ぶチャンスがないまま、いきなり“作文”を求められても、どう書けばいいかわからないのは当然です。
語彙や文法の感覚があいまいになっている
海外在住の間、語彙が英語中心になることも多く、表現の幅が狭くなりがちです。
特に中学生になると、語彙の豊かさや表現力が求められますが、海外在住の間に「感覚」で日本語を話していた子ほど、文法的な正確さや語彙の広がりにギャップが生まれやすくなります。
「すごい」「かわいい」「やばい」など、少ない語彙で感情を表すクセがついてしまっているケースも。



これは帰国子女だけではなく、若い子たちの特徴でもあるんですよね。
また、主語述語の概念があまりないのかもしれません。



英語ではしっかり主語を言ってるのに、日本語になるととたんに主語がない話ことばになるのはなぜなんでしょう。
これが作文や記述式問題で「言葉が足りない」「内容が薄い」と評価される原因になります。
学校の国語授業の進め方にギャップがある
日本の学校では、記述問題・読解・文法用語など、形式的な学びが多いのが特徴です。
自由に考え、自由に発言してきた海外スタイルに慣れていた子にとっては、「答えを合わせる」ことが重荷になることも。



実はこれって逆もしかり、で、英語も会話中心でしかやらないと、英語資格を取るときなどに必ずどこかでつまづきます。
小学校低学年で帰国した子がすぐ英語を忘れてしまうのは、まねっこ会話で終わってしまい、文法などの知識が養われていないから起こるとも言われています。
「作文が書けない」をどう乗り越える?5つのアプローチ
「書こうとしても言葉が出てこない」「何を書いていいかわからない」…



そんな作文の悩みは多くの帰国子女が感じていること。
ここでは、親子でできる具体的なステップを5つご紹介します。
① 起承転結の“型”を学ぶ
作文の基本は「起承転結」です。
これは、ストーリーを展開させる基本的な枠組みで、多くの場面で役立ちます。



帰国子女が、日本語の作文に苦手意識を持つ理由の一つは、文章の流れや構成に慣れていないことです。
文章の型を知ると、「何を書けばいいか」が明確になります。
まずは、この「起承転結」の構造を理解し、文章を組み立てる練習をしましょう。



起承転結といえば4コマ漫画!
読むはももちろんですが、自分で4コマ漫画を描いてみるのもおすすめです!



また、作文を難しいものだと考えず、お絵描きをするような感覚で、自由に空想して書いてみるのもおすすめ。
思わぬ素敵な表現が浮かんできたり、面白い言葉を作ったり、自分の言葉・感性を表現して相手に伝えるスキルは、かけがえのない財産になります。
② 好きなテーマで自由に書かせてみる
いきなり「感想文を書いて」と言われても難しいもの。
まずは、好きな食べ物や遊び、旅行の思い出など、身近なテーマで「自由に書いてみる」ことが大切です。
「自分の言葉で書けた!」という体験が、書くことの楽しさにつながります。
③ 親子で「話す→書く」の習慣をつける
作文が苦手な子は、まず口で話す練習から始めるのが効果的です。
- 今日楽しかったことを話す
- それをメモにして、短く書いてみる



この「話す→まとめる→書く」の流れを繰り返すと、自然と文章が書けるようになります。
ちょっと子供には難しいかもしれませんが、まず大人が読んで「書くことの楽しさ」を実感してみませんか?
▷ ④ 読む力を同時に育てる(音読・読書)
読む力=語彙や文の構造を学ぶ基礎です。
好きな本を音読したり、同じ作家の作品を読むことで「こんな表現使ってみたい!」という意欲が生まれます。
⑤ 日本語の構造を理解する
帰国子女の方々が日本語の作文に苦手意識を持つ理由の一つに、日本語の文法や表現の違いがあります。



特に英語に慣れている場合、日本語と英語の文法構造の違いに戸惑うことが多いです。
日本語の主語・述語の位置や敬語の使い方、てにをは(助詞)の使い方を理解するために、日本語の文法書や参考書を活用して、基本的な文法の違いを学びましょう。
作文・国語力向上におすすめの教材&サポート



国語力や作文力を伸ばすには、我が子に合った教材やサポート選びも重要なポイントです。
この章では、小学生にも中学生にも対応できる、おすすめ教材やオンラインサービスを紹介します。
無学年で振り返り学習・漢字アドベンチャーも実装【すらら】
- 対話型の映像授業で“言葉のしくみ”から理解できる
- 無学年制だから小1〜中3の苦手範囲を自由に復習可能
- 書く力と読む力を同時に育てたい子におすすめ
- 帰国子女サポートもあり、通信教育ではあり得ないほどの手厚いサポート


漢字・語彙・検定対策まで対応:スマイルゼミ
- タブレット学習で漢字・語彙・読解を繰り返し学べる
- 漢字検定や英検など、資格試験対応のコンテンツも充実
- 学年を超えた学びにも対応し、家庭学習の定着に役立つ
>>【スマイルゼミ】
![]()
![]()
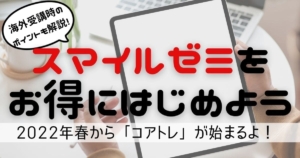
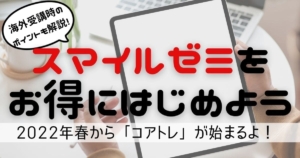
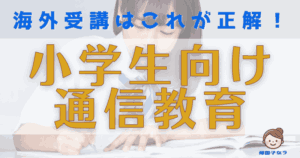
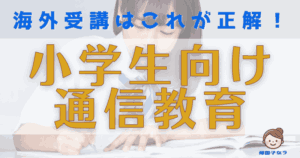
自分に合った先生とマンツーマン指導:マナリンク
- 教員免許や指導経験がある先生が多数在籍
- プロフィールを見て、相性の合う先生を選べる安心感
- 国語・作文指導にも対応しており、海外からの指導実績も多数
>>【マナリンク】
![]()
![]()
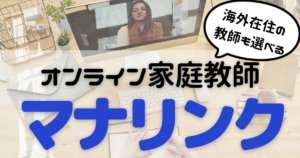
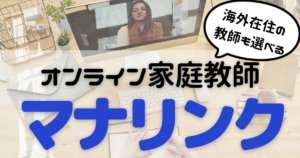
授業レベルが高く、定評のある国語授業:東進オンライン学校 小学部・中学部
- 一流講師による動画授業で、わかりやすく本質を教えてくれる
- 小学部・中学部ともに国語の読解・作文に対応
- 自宅で自分のペースで進められるので、海外生活中にも取り入れやすい
勉強習慣づけ&丁寧な国語サポート:オンライン家庭教師Netty(ネッティー)
- 昭和54年創業のノウハウで、安心の指導体制
- 1対1でじっくり進められるから、作文や読解の苦手克服にぴったり
- 海外からの受講実績もあり、時差対応も柔軟


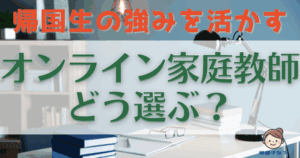
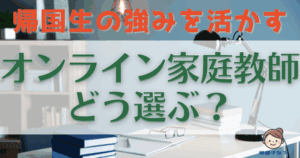
まとめ:海外育ちでも作文力は必ず伸びます!


帰国子女が作文力を向上させるためには、基礎的な作文の構造を理解し、語彙力を増やし、日本語の文法に慣れることが重要です。
また、自分の好きなトピックで書く楽しさを見つけたり、添削を受けてフィードバックを活用することも効果的です。



ただ、これをすべて個人でやるのはとっても大変。
通信教育を利用したり、家庭教師と会話しながら国語力をあげていったり、ぜひ工夫してみてください。



また、帰国受験で小論文が必要な場合は、帰国受験専用の小論文の書き方があるので、プロに相談してください。
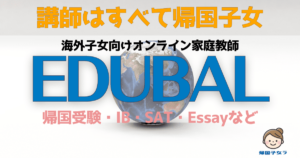
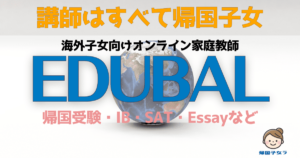
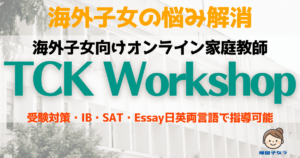
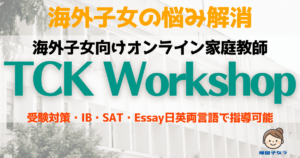
すべての教科に必要なのが「国語力」



国語力をつけることは一生の財産になりますよ!
帰国子女の経験値+英語力+国語力で、最強の武器を手に入れましょう。




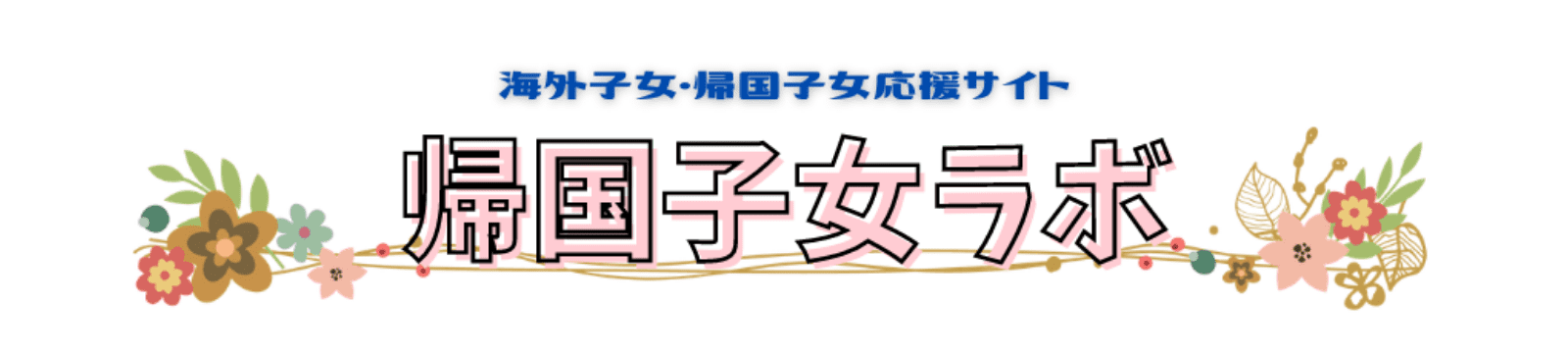
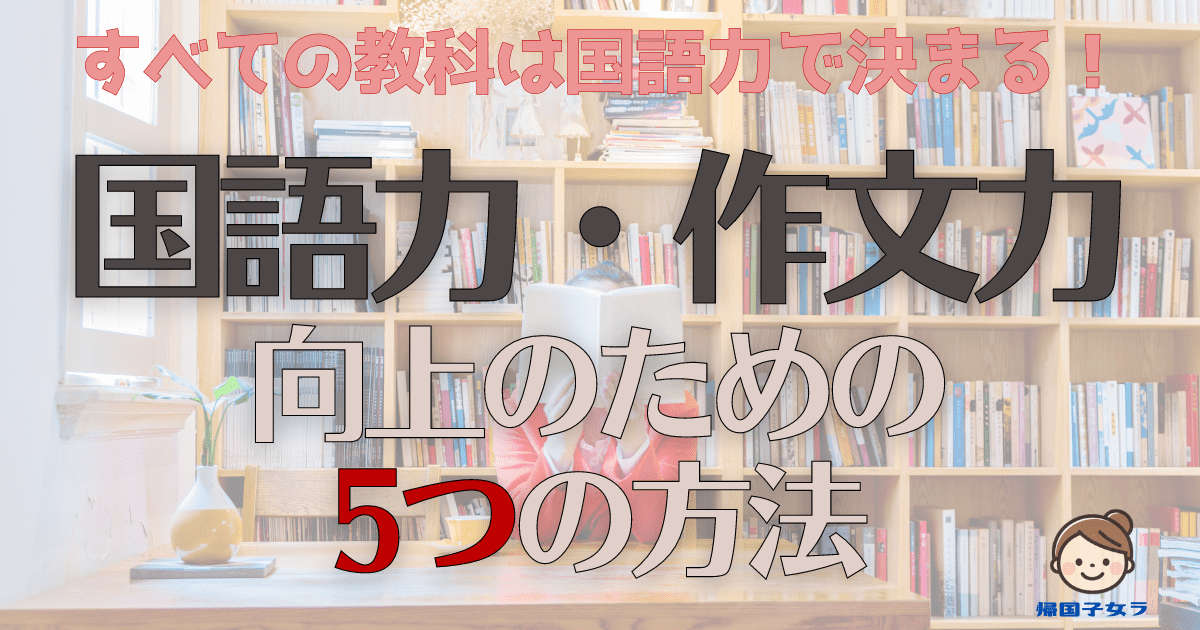












コメント